・知育ってなんだか難しそう…
・やってみたいけど
忙しい中でできるかな?
・今さら、知育って遅いの?
知育をはじめてみたいけど、何からしていいかわからない!
そんなことはありませんか?
この記事では、「知育って何?」「早期教育って何?」
そんな疑問を解決していきます。
さらに、0歳から6歳までの
年齢別の知育のポイントと遊びのヒントを紹介。
年齢に合わせた具体的方法もわかることで
「我が子にどんな知育したらいいんだろう?」そんな不安が解消され、
今日から無理なくおうちで知育をスタートできます。
『知育って何?』知育の基礎知識
知育とは、子どもの知的能力を育む教育
のことです。
教育の基本と言われる三育のひとつと言われています。
三育って何?
三育とは『知育、体育、徳育』の3つから
構成されており教育の一種
三育をバランスよく育てることは
子どもが『生きる力』を身につけらる上で
重要です。
そもそも三育は、イギリス学者である
ハーバート・スペンサーが提唱し
日本では明治時代に学問のすすめ
(著:福沢諭吉)の中で取り上げられ
広まりました。
また、0〜6歳ころの教育のひとつとして『早期教育』があります。
早期教育と知育は何が違うの?

早期教育は幼少期からそろばん、ピアノ、
英語、計算といった教育を取り入れること。
1980年〜1990年代にフラッシュカードやドッツカード、そろばん、英語教育などが
家庭教育として人気で注目されていました。
その後、2020年のコロナ禍以降は
おうち時間が増えたことでおうちでできる
早期教育がSNSなどを通して話題となりました。
一方で知育は遊びや生活を通して、考える力や好奇心、探究心を育むこと
以下の表なイメージです
| 早期教育 | 知育 | |
| 目的 | スキル、学力の早期取得 | 好奇心、探究心といった生きる上での力を育む |
| 方法 | 教材を使ったり、教室に通う | 教材や玩具を使う、教室に通う、暮らしの中で行う |
知育は、知識を学ぶのではなく人生を
豊かにしていくための力を養っていきます。
AI技術が発展する現代で、予測不可能な未来を生きていく子どもたちには、
言われたことをこなすだけでなく、自分で考え、新しいものを生み出す力が
ますます求められます。
そんな変化の大きな未来を生き抜くための必要な力を養う準備が
知育と言えるのです。
【知育の目的】なんで知育が必要なの?
知育は子どもたちが隠れ持っている可能性を引き出し
その力を大きく伸ばすためにも大切です。
知育でどんな可能性が引き出されるのかについて
解説していきます。
知育で育まれる5つの力について
知育で育まれる力は以下のものがあります。
- 思考力、考察力
目に見えることだけでなく、物事が起きた過程を考える力。
例えば、積み木を積む中でなぜうまく積むことができたのか
失敗を繰り返す中で学んでいきます。 - 好奇心、探究心
「なぜ?」「どうして?」といった物事や学びのエンジンになる好奇心、探究心。
知育は、子どもたちのそんな純粋な気持ちを大切にし、自ら学びに向かう意欲を
育てることができます。 - 表現力、想像力
答えのないものに自由な発想をし表現する力。
粘土遊びやお絵描きを通して育むことができます。 - コミュニケーション能力
生きていく上では欠かせない力。
お友達やママ、パパとのやりとり、絵本の読み聞かせを通して
いろんなコミュニケーションを学んでいきます。 - 自己肯定感
「自分はできる!」と自分自身を自分が信じてあげられる力。
自己肯定感は困難に立ち向かう時、新しい挑戦をする時は欠かせません。
褒めてもらえる経験、応援してもらえる経験が自己肯定感を育んでいきます。
幼児期における知育の必要性

0〜6歳の幼児期と呼ばれる時期になぜ知育が重要視されるのか。
その理由は、6歳くらいまでが子どもの脳の発達において非常に
重要な時期とされているからです。
特に五感(視る、聴く、触る、味わう、嗅ぐ)を刺激する知育は脳の発達を大きく促します。
(例)
・色のカラフルなおもちゃをみる
・いろんな音を聴く
・砂や水など違う性質のものを触ってみる
0〜6歳時期の子どもたちにとって遊びは
単なる暇つぶしではなく、日々の学び。
「仕事や家事で忙しく子どもにゆっくり関わる時間なんてもてない!」
そう思うママもいると思います。
ですが、子どもの話を聞いたり、できたことを褒めてあげたりすることは
子どもたちにとって『安心できる環境』であり、安心できる環境があるからこそ
学びへの意欲が高まります。
日常生活の中に知育となる要素が
実はたくさん含まれているのです。
【年齢別】知育のポイントと遊び方のヒント
0〜6歳の子どもたちは心も体も大きく成長する時期でそれぞれの年齢で
できることが変化していきます。
今回はわかりやすく年齢別にまとめて知育の基本をお伝えしていきます。
0歳〜1歳

この時期は『安心、安全できる環境で五感を刺激してあげる』ということが基本。
言葉を通してのコミュニケーションがまだ難しい時期ですが、触れ合いや音を通してたくさんのことを吸収しています。
また、この時期の赤ちゃんは視力がまだ十分に発達していないので『カラフルなものを使う』『関わりはお顔を近づけて』といったことが大切になってきます。
- ベビーマッサージ
ベビーマッサージでママやパパの手の温もりを感じることで赤ちゃんは安心感を得ることができる。 - 触れ合い遊び
リズムやお歌に合わせて、赤ちゃんの手や足を動かしてあげたり、素材の違うもの(タオル、ガーゼ、ビニール)を触ったりすることで触覚を豊かにする。 - おもちゃ
生後間もない赤ちゃんたちは視力が0.01程度、生後7ヶ月以降で視力が0.1程度と言われているので『カラフルなおもちゃ』がおすすめ。
2〜3歳

言葉の発達、手指の発達が盛んで、『なんでも自分でやってみたい!』そんな気持ちが芽生える時期。
それと同時に自我が芽生え始め、自分の思い通りにならないと泣いたり怒ったりして表現する『イヤイヤ期』でもあります。
子どもたちの『やりたい!』といった気持ちを尊重するのはもちろん大切。
自我が芽生える時期にじっくりと向き合うのは大変なのでママも肩の力を抜きながら関わってみてくださいね。
- 粘土遊び
捏ねたり、きったり、潰したり、いろんな過程を通して手指の感覚、想像力を育む。 - 散歩
道端にあるさまざまな物に興味を示してお散歩の中で出会うものやことに指さしで教えてくれる時期。
『赤いお花だね!』『わんわんだね!』と応えてあげることで物と言葉が結びつき、言葉を覚えていくことができる。 - 絵本
物語を楽しむだけではなく、新しい言葉に触れることで言葉を吸収していく。
4〜5歳

想像力や思考力がぐんと伸びてくる時期。
保育園や幼稚園でお友達との関わりも増えてくる時期であり、ママやパパ以外の人との関わりを通してコミュニケーション能力も育まれます。
知育を通して想像力を広げ、自分で考える力がどんどん養われます。
- ごっこ遊び
役になりきって遊ぶことは表現力や想像力を豊かになる。 - 製作遊び
廃材を使って自分で何かを生み出すことは想像力を育む。
また、ハサミや道具を使うことで手先を器用にする。 - パズル
空間認識能力を育んだり、達成感を味わうことができる。
6歳

小学校入学前で学習への興味関心が一気に高まる時期。
遊びの中でも学習への興味が繋がることが大切です。
- ルールを決めて遊ぶ
カードゲームやボードゲームといったルールを決める遊びを通して、社会性や思考力が育まれる。 - 文字や数に触れる
絵本やドリルの中で数字や文字に触れることで、学習への抵抗を減らし、学びの楽しさを引き出すことができる。
年齢別の知育のポイントをまとめてきましたが子育てをしているとどうしても『周りと比べてしまう』
そんなことありますよね?
そんな時に知っておいてほしいことについて
3つお伝えしてきます。
知育をはじめる前に大切な3つのこと
子育てには正解はないと言われるけれど
子どもの成長発達のことは比べてしまう。
そんなママも多いのではないでしょうか?
知育を通して我が子と向き合う中で
『周りと比べてしまう』そんな状況になった時
以下の3つを意識してみてくださいね。
焦らず、我が子のペースで
0〜6歳児期は心と体が大きく成長する時期だからこそ、個人差がとても大きいです。
「あの子はできてるのにうちの子はまだできない…」
そんな感情になることもあると思います。
でも、大切なのは周りを見ることではなく昨日の我が子と今日の我が子を比べてあげること。
その視点に変えるだけで、我が子の成長した部分をたくさん見つけることができ小さな成長を共に喜び分かち合えることができます。
完璧主義にならない
知育をやろう!と教材やおもちゃを準備していると、ついあれもこれもと完璧を求めがちになります。
でも、実は日常の中に知育のポイントがたくさん溢れています。
お散歩の途中で見つけた小さな発見、料理のお手伝い中といった
日常生活の中に学びのポイントがたくさんあるのでぜひ意識してみてくださいね。
ママやパパがまずは楽しむ
知育は教育の中のひとつだからこそ、ママやパパは真剣に、熱くなってしまいがちですがまずはママやパパが全力で楽しむことが大切です。
子どもたちはママやパパの楽しんでる姿を見て『自分もやってみよう!』そんな気持ちになります。
そして、ママやパパの笑顔が子どもたちにとっての安心材料になり学ぶ力をより引き出してくれます。
まとめ
知育は決して難しいことではありません。
日常生活の中から知育に繋げられることがたくさんあります。
仕事に家事に追われていて子どもとの時間が十分に取れない。
そんなママやパパでも日常生活の小さな工夫が知育の第一歩となります。

難しく考える前にまずは、我が子と共に知育を楽しむことから
一緒にやっていきましょう〜!

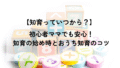
コメント